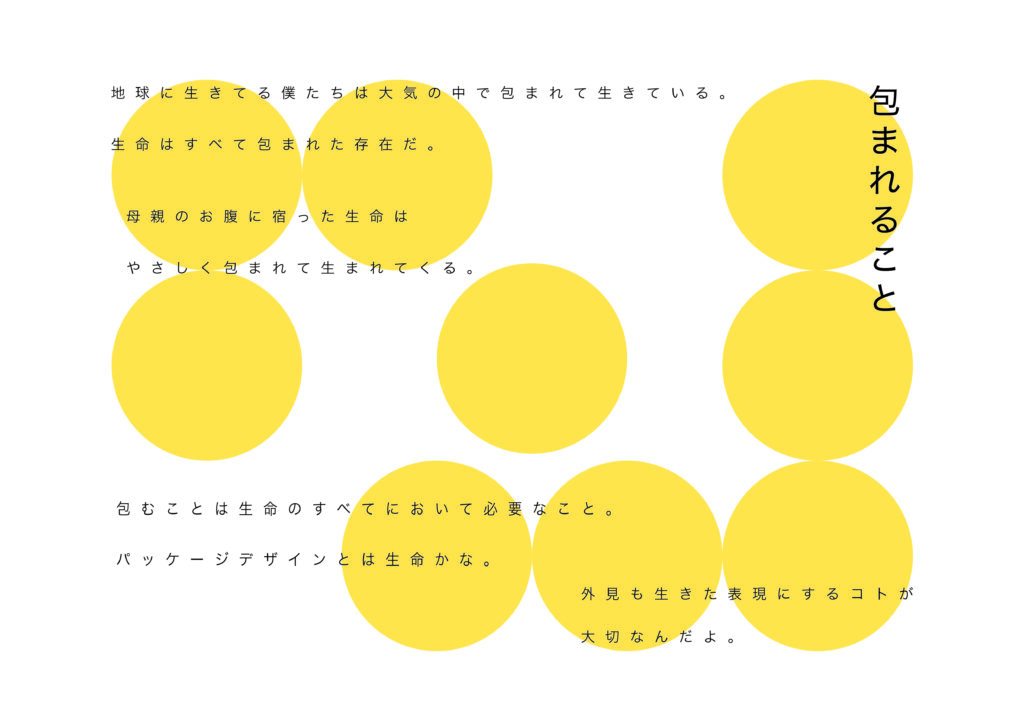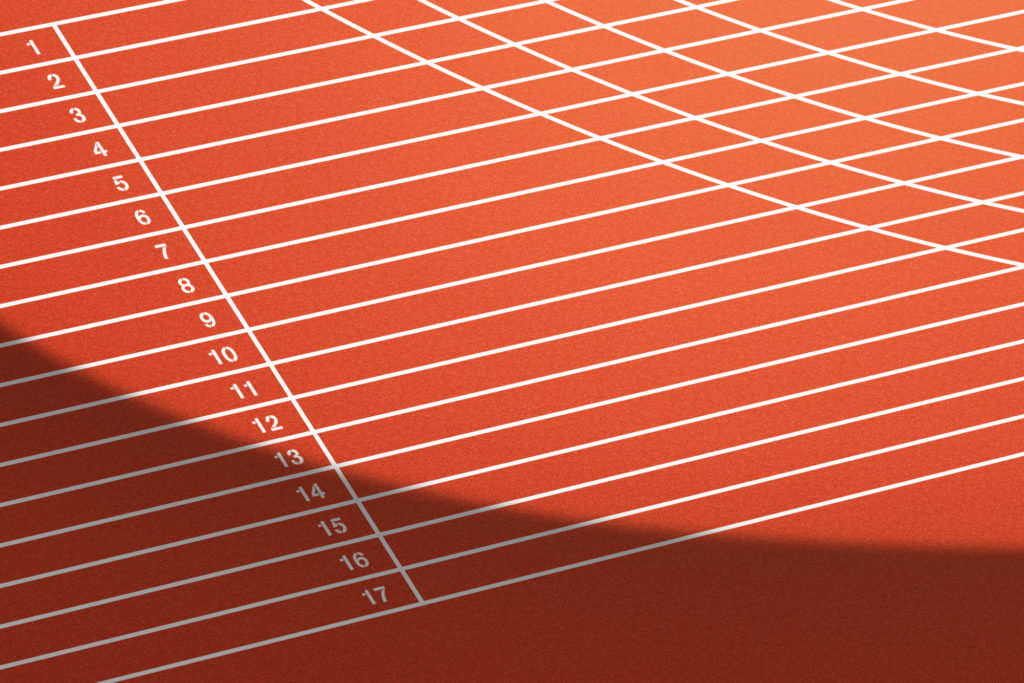KURAND×P.K.G.Tokyo デザインとブランドのいい関係とは


P.K.G.Tokyoのメインワークである、パッケージデザイン。
今回は、氷点下で約20年眠り続けた熟成日本酒「FRESH VINTAGE the epic」のデザインとブランドの関係性の観点から、商品開発のストーリーをお送りいたします。KURAND株式会社の商品チームマネージャーの青砥 秀樹さんと、弊社ディレクターの柚山の対談形式です。
取材・文:大島 有貴
インタビュー撮影:唐 瑞鸿(plana inc.)
商品撮影:近藤 伍壱(ROBIN HOOD)
FRESH VINTAGE the epicとは
「FRESH VINTAGE」は、しぼりたてそのままの日本酒を-5℃の氷点下の中で長期間熟成することによって誕生した、“ビンテージなのにフレッシュ”といった、相反する新しい味わいが特徴の日本酒シリーズ。「FRESH VINTAGE the epic」は同シリーズのはじまり1本。20年間氷温熟成され、200本限定生産の貴重な日本酒である。販売価格は11万円(税込)。


<プロフィール>
KURAND株式会社 商品チームマネージャー 青砥 秀樹さん(写真右)
島根県・青砥酒造で6年間酒造りに従事し、ゼロから新銘柄「蒼斗七星(あおとしちせい)」を造り出し、日本酒業界で多くのファンを生み出す。青砥酒造を退社後にKURAND株式会社に参加し、商品チームマネージャーとして全てのプロダクト開発を担当。お酒をアップデートする、次代のプロダクト開発を手掛ける。
P.K.G.Tokyo ディレクター 柚山哲平(写真左)
2009年、柚山デザイン株式会社を設立。さらに2017年、P.K.G.Tokyoを創業メンバーとともに設立。ブランディングを中心に、ブランドコンサルティングや商品プランニング、アートディレクションからデザインまでシームレスかつ幅広く取り組んでいる。P.K.G.Tokyoでは、これまで様々なメーカーの主要商品ブランディングやパッケージデザインを手がけてきた。
FRESH VINTAGEシリーズ立ち上げに関わってきた経緯
柚山:本日はどうぞ、よろしくお願いいたします。KURANDさんと弊社の出会いは、日本酒「金銀 -KEEN GUIN-」パッケージデザインのご相談がきっかけでしたね。私が担当として、御社と初めて関わったタイミングは、FRESH VINTAGEシリーズ立ち上げでした。
青砥:そうでしたね。その際に、ストラテジー策定から関わっていただいて。私どもと、酒蔵である中野BCの担当者、そしてP.K.G.Tokyoさん同席でワークショップを行っていただきました。ペルソナ設定から「FRESH VINTAGE」というネーミングに至るまで。ストラテジー策定から関わっていただけるデザイン会社さんは、他にあまりないので、とても説得力のあるデザインに仕上がったと思っています。
 FRESH VINTAGEシリーズ。
FRESH VINTAGEシリーズ。
デザインに関するストーリーはこちらから
肌感覚で得てきた、デザインとブランドの関係性の大切さ。
柚山:KURANDさんも、全国の酒造会社と提携し、商品企画、製造、物流、販売までを一気通貫するプラットフォームをつくられていて、他に例がない会社さんだと思っています。近年ですとオンラインでの「酒ガチャ」も話題になりましたよね。
青砥:今まで商品開発から関わり、生み出してきたお酒の数は500種類ほどあります。1本1本のお酒に合わせて、提携酒蔵との密なコミュニュケーションをとり、ひとつひとつのブランドを丁寧につくりあげているのです。
加えて、オンライン酒屋「クランド」や、オウンドメディアを運営しております。デジタルの活用はKURANDには欠かせないものです。「一体、何屋さんなのか?」と聞かれることが多いのですが、私たちはまず、酒屋であることがアイデンティティー。社長荻原の創業の目的はシンプルに「お客さまにお酒の魅力を知って、飲んで、喜んでもらいたい」ということ。特に、酒蔵さんがリーチしづらい若いお客さまへ伝える手段として、デジタルを使っていこうと。「お客さまに喜んでもらうため」に、様々なトライアンドエラーを積み重ねて10年やってきました。
実は、今のようなビジネスモデルになるまでには、通常の酒屋と同じように、代表的な銘柄(ナショナルブランド)を販売していた時期もありました。ですが、その方法ですと、他との差別化が難しい。そこで、さまざまな試行錯誤の後に、現在のようなビジネスモデルが出来上がったのです。今までの経験の中で、お客さまにお酒の魅力を感じてもらうには、中身の質の良さはもちろんのこと、ネーミングからデザイン、ストーリーを伝えることが大切だと肌で感じてきました。ですので、私たちは提携の酒蔵とブランド企画を共にし、ブランドの具現化としてのデザインをとても大切にしているのです。

柚山:なんだか、今の話を聞いて合点することありますね。KURANDさんとの仕事はデザインに至る過程を大切にする我々にとって、とてもやりやすかった。というのも、一緒にものづくりをする、酒蔵との議論の場に、私たちデザイナーを同席させていただいたんです。ところで、青砥さんはお酒の「造り」についても大変お詳しいですが、そこまでの知識はどこで学ばれたのでしょうか。
造り手と伝え手のコミュニケーションの密度
青砥:実は以前、酒蔵の現場にいました。弊社には同じように「酒造り」に携わっていたメンバーが私含め3人おりまして、そこは強みだと感じています。というのも、製造自体は提携酒蔵に委託はしているがゆえ、酒蔵の方と対等なコミュニケーションが取れることが、1本1本に合わせたブランドづくりを強固にできると思うのです。
柚山:すごく分かりますね。デザインの世界でも、デザイナーは最終的なアウトプットのことを深く知っておく必要があります。グラフィックデザインであれば紙や印刷の知識は不可欠だし、プロダクトデザインなら使用される素材の特性や製造工程を知っている必要がある。同じように、伝え手としての側面を持つKURANDさんが、最終アウトプットを担う酒蔵と密なコミュニケーションを取れることで、いいものがつくれるのですね。
20年間、大切に寝かされ、眠っていた熟成酒。
青砥:「FRESH VINTAGE the epic」の製造を委託しております酒蔵は、和歌山県の中野B Cさんです。弊社とは長年の信頼関係があります。酒蔵のある紀州は温暖な気候。その気候が影響し、夏を越すとお酒が過熟状態となり、色付きや味わいに重みが出ることに長年悩まれていた。そこで酒蔵としては本当に先駆者と言ってもいいほど昔から、氷温でお酒を寝かせて熟成することにトライされてきたのです。その氷温室で20年間眠っていた酒が今回の「FRESH VINTAGE the epic」。初めて飲んだ時、「これはすごい」と純粋に感じました。このお酒を「ぜひ、お客さまに飲んでいただきたい」と。
正直、熟成酒といっても、保存状態がずさんであったりするとその価値を感じられない味であることが、よくあるのです。ですが、このお酒は大切に寝かされ、「眠っていた」という言葉がまさしくで。私たちが官能的に感じる価値と、価格といった数値的な価値がイコールであるならば、これは何としてでもやりたいと。デザインを含め、どのようにお客さまに伝えていくのかは私たちの腕の見せどころ。「ぜひ、僕たちにやらせてください」と酒蔵にお伝えしました。私たちもここまでの高価格帯のお酒を売った経験はなかったので、その時はノープランだったのですが…。そうしたら、「KURANDがそう言うんだったらいいよ」と酒蔵が快諾してくださったんです。

今までにないお酒だからこそ、その価値を体現したデザインを
柚山:実は、一旦提案した別のデザイン案がありました。そこから、少し時間をおいて見返したとき、このデザインは果たして青砥さんたちが見つけたお酒のポテンシャル、価値を本当に表現できているんだろうかと。そこで、自主的に再提案させてくれないかという話をしたのです。今までにないお酒なのだから、ラベルの表現も今までにないことをやらないと、その価値には届かない。革を使った理由としては、今までにない、20年の熟成酒であることを表現するためです。時間を経ることで深まる価値を表現するにあたり、風合いの変化が楽しめる革という素材が、今回のテーマにふさわしいと考えました。ですが、やはり前例がないので、クリアしなければいけないハードルが盛りだくさんでしたね。革と酒、両方の品質保持。冷蔵輸送の際に懸念される結露など。そういった商品として乗り越えるべきハードルをクリアするため、実験を繰り返し行ってもらい、ようやく形にすることへとたどり着いたデザインなんです。

ラベルにはヌメ革を使用している。最初はやさしいベージュをしているが経年変化とともに美しい飴色になっていく。商品名など文字情報はすべて型押しで構成されており、印刷を使用しない特殊なラベルである。
青砥:具体的には、酒蔵で実際に20日間〜1ヶ月冷凍保存して、革に変化がないか、匂いなどに問題がないかという検査をしました。加えて、輸送テストも行いました。ここは、ちょっと厳しい私が出てきてしまってですね、厳格にチェックをさせていただきました(笑)。やはり高価格帯の商品なので、お客さまの手元に届いたときに、商品の価値を最大化したい。どうしても、配送時のトラブルがあったり、酒蔵の管理上の限界があったりするので、そこがきっちりと大丈夫かを確かめておきたかった。そのために、今までの商品開発の中で一番時間がかかり、1年半を要しましたね。
商品企画のはじまりに、デザイナーが同席することの重要性
柚山:例えば他のクライアントに「革のデザインでいきましょう」と提案したとすると、前述のような苦労がつきものなので、普通は採用されません。ですが、KURANDの方々は「やってみましょう」と前向きに、一度飲み込んでくださるのです。みなさん、商品のストーリーをデザインに落とし込む重要性をよく理解されているのだと感じました。実は一般的なデザインの仕事は、決まった条件のもと依頼されることも多いのです。ネーミングや表現媒体も決まっていて、その範疇でデザインをお願いしますと。デザインが上手くハマれば良いのですが、マーケティング的観点で立てた仮説と、用意された条件が矛盾していることもしばしば。本当にブランドの価値を最大化したいのであれば、商品企画の段階からデザイナーが議論の場に立ち会う必要があるのではと私は考えています。仮に決定権がなかったとしても、初期の議論に参加することができれば、ボタンのかけ違えや矛盾は起こらないと思うのです。ですので、KURANDさんのように、膝突き合わせながら進めていくプロセスは、ブランドの価値を無理なくデザインに昇華させることができると感じています。

青砥:私たちにとっても、企画の最初の段階から一緒に考えていただけるデザイン会社さんは逆に言うと他にないんですよね。実は、今回「FRESH VINTAGE the epic」のネーミングは、柚山さんにご提案いただいたんです。基本的に今までの商品の名前は多くの議論の上、ほぼ社内で決めています。しかし、今回ご提案いただいた「the epic(叙事詩)」という名前。つまり時代を経て語り継がれる物語というネーミングが、熟成を重ねて味わいが増すこのお酒には相応しい名だと思いました。
残り1%、0.1%に違いが出る。それが「人」がやる意味ではないのだろうか。
柚山:ありがとうございます。少し唐突に話が逸れてしまうかもしれませんが、個人的な最近の興味として、AIをはじめとするテクノロジーの進化というものがあります。目まぐるしい進化の中で「人が行う表現の意味」を考えるのです。つくることから選ぶことにシフトし、条件さえ揃えば誰でも模倣できてしまう表現という渦の中で、言い換えるなら「違い」とはどうやって生まれていくのかと。
青砥:私たちの仕事にも同じことが言える部分がありますね。99%近くまでは、きっと同じ情報などのインプットをしたら、多くの人は導き出せてしまう。だけど残り1%、0.1%に自分たちが入る余地があると思っていて。それが何なのかと考えた時に、言葉に表現しようがないからこそ「個性」とか「センス」という言葉を使うんですよね。お酒造りも同じような条件、環境で造ったお酒でも「誰が」造ったかによって味の違いが出るのです。 そこが面白い。
柚山:なるほど。少しの差が唯一無二の個性を生む。面白いですね。これからもKURANDさんとは、ディスカッションしながら新しい商品を一緒に生み出していただけたらいいなと思っています。どうぞ、よろしくお願いいたします。

K U R A N D株式会社の情報はこちら
「FRESH VINTAGE the epic」の情報は こちら