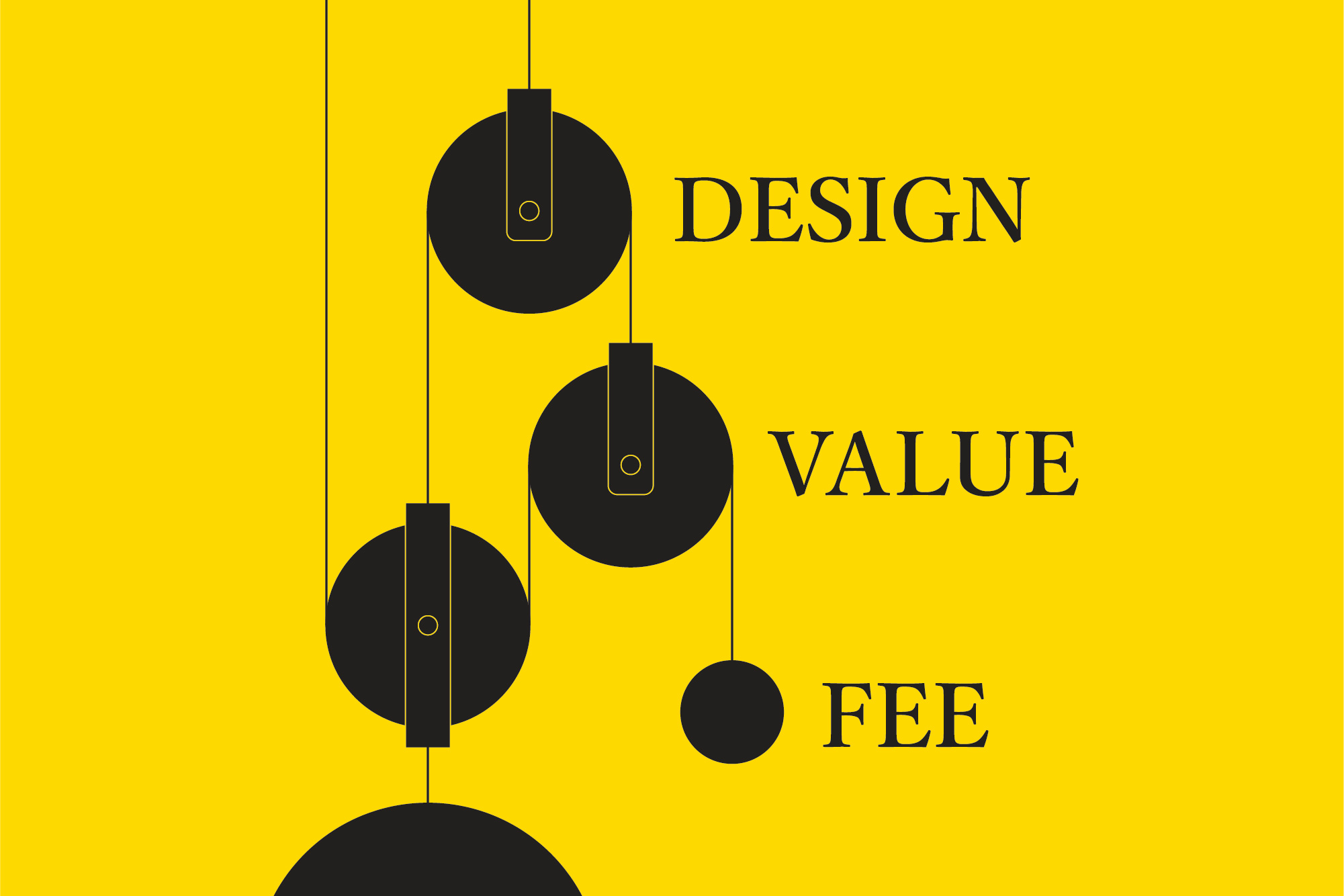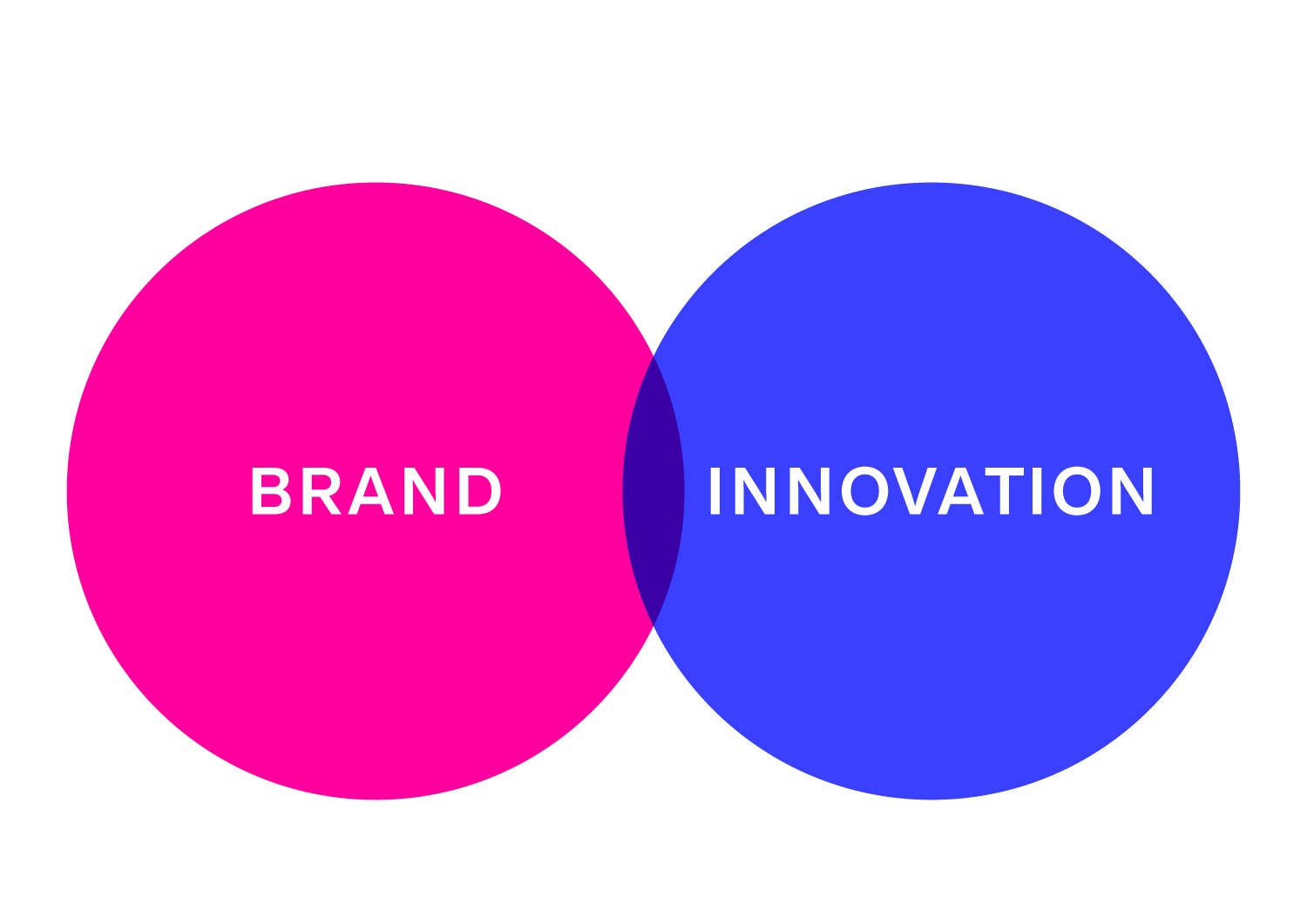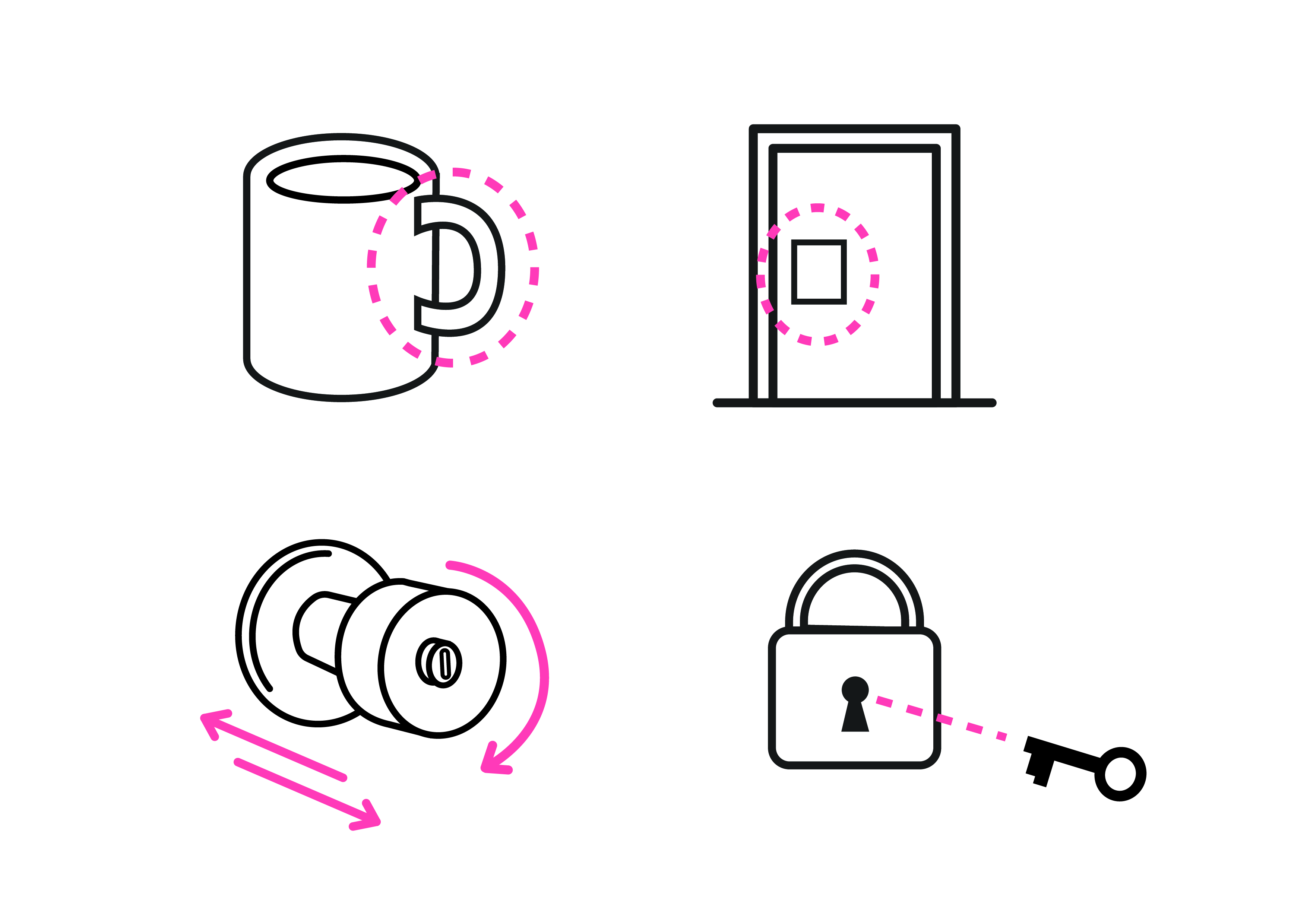時代と共に様々なサービスやシステムが大きく変わろうとしています。
今回はわたしが日々の生活の中で面白いと感じた、これまでとは違う新しい「サービス」を紹介します。
オンライン寄せ書き「yosetti」
https://www.yosetti.com

こちらはオンラインで寄せ書きを作成するwebサービス。
web上で集めたメッセージデータをpdf化、実際に寄せ書きとして形にして相手に発送できるもので、友人の結婚祝いにあたりこのサービスを知りました。色紙を購入→メッセージを書き次の人へ回す→全体を装飾する、、様々なプロセスを経て行う「寄せ書き」ですが、オンライン上で簡単に作成が可能になりました。背景のデザインや文字の色は自由に選択し、写真の添付も可能。当初はオンラインの寄せ書きというイメージが、どこか希薄なのでは?疑心暗鬼でしたが、実際に使用する、手軽に使えること、書き直しが出来ること、出来上がったものを見られるなど、メリットも多く面白いサービスだと感じます。また物理的な距離があっても簡単に寄せ書きが出来るのは、大きなメリット。なるべく人との接触を避けなければいけない、今の時期にも使いやすいですね。
お花のサブスクリプション 「ハナノヒ」
https://www.hibiyakadan.com/shop/hananohi

最近よく耳にする「サブスクリプション」。月定額制アプリを使い、店頭で好きなお花を選び、スマートフォンでタッチで決済し購入できる仕組みです。これまで「花」を買うことがどこかハードルがある、また中には気恥ずかしいという人も多かったようですが、手軽さが人気で店頭で男女問わず、仕事帰りの方がスマートフォンを片手にさっと買っていく姿が多く見られ、印象的でした。数本から気軽に購入できることや、決められたお花が届くのではなく、自分で無理のない範囲で「選べる」のも人気の理由かもしれません。
これまで直接人対人のコミュニケーションを通さなければ出来なかったような仕組みが変化しています。そしてオンラインやデジタルの要素を取り入れたサービスに触れると、パッケージデザインにも新たな「仕組み、サービス」が出来るのではないかと感じました。オンラインで商品を見ながらの買い物はあたり前になってきましたが、ネット上の仮想空間で実際に商品を手に取るように買い物をし、商品を選ぶ時代もそう近くないのかもしれません。ラベルレスパッケージが登場した今、紙ではない新たな未来のパッケージなど色々な可能性も考えられます。
パッケージデザインの持つ素材の手触りや温もり、それが手に取る人に与える影響。それはとても大きな意味があるように思います。その一方、オンラインやデジタルにおける新たな視点を持つことも必要になっていくのだと感じました。私たちに大きな影響を与えたこの変化とともに、様々なサービスやものの在り方を考えていく転換期が訪れています。
P.K.G.Tokyo 大西 あゆみ