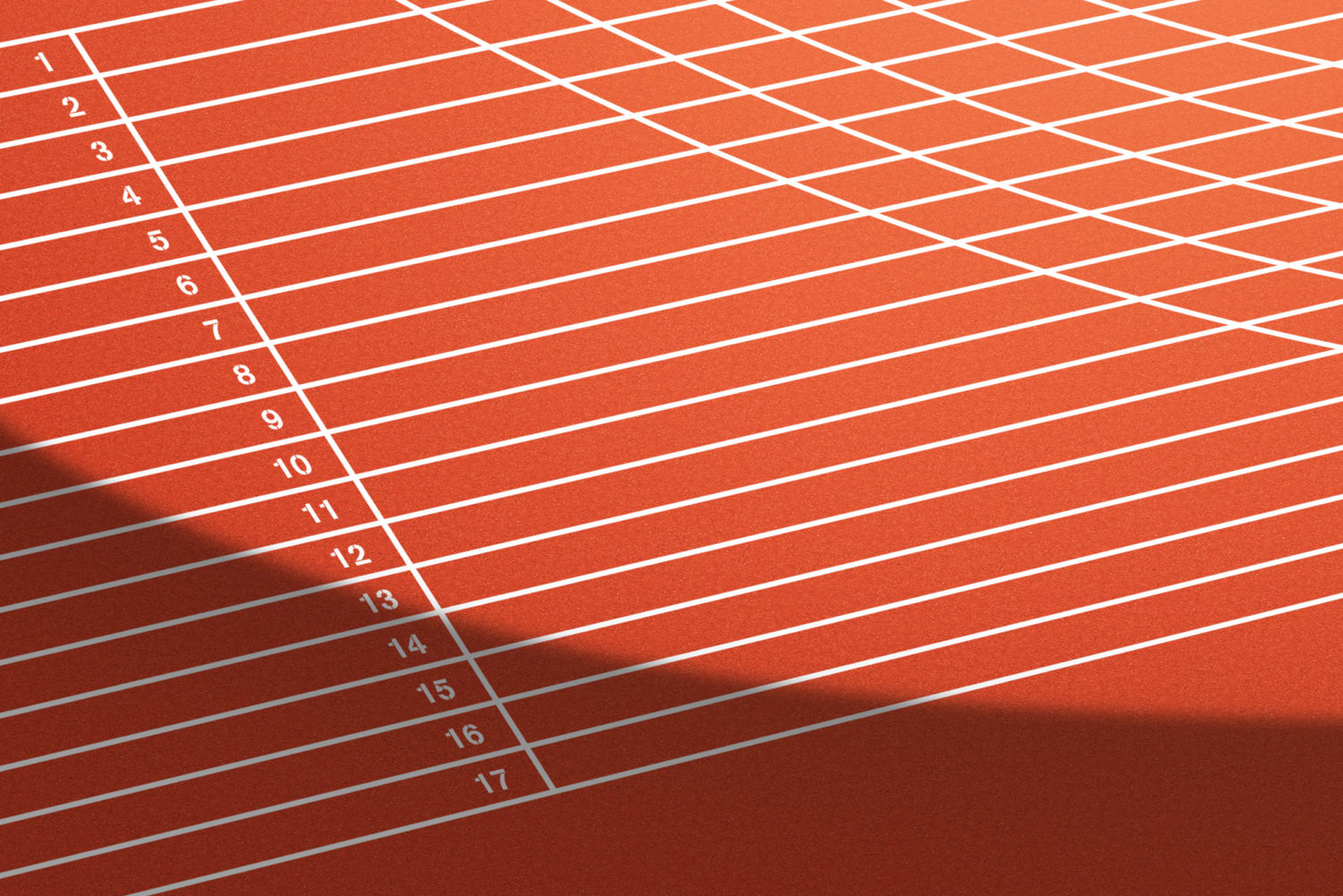i3DESIGN × P.K.G.Tokyo 浸透するパーパスを作り上げ、運用していくには

「パーパス」という言葉をご存知でしょうか。企業の存在意義、社会に対する宣言を意味します。P.K.G.Tokyoは「世の中のあらゆる価値をデザインで更新し、世界のすみずみへ届ける。」というパーパスを掲げています。「design」の語源はラテン語の「designare」。「計画、設計を記号にして表す」という意味。現在の「デザイン」とは、ビジネスモデルをはじめとした、目には見えないものを計画、設計することも含まれると言えるのです。
そんな意味においてP.K.G.Tokyoは「パーパスを可視化する。ブランドをマネジメントする。」を掲げ、パーパスブランディング事業Identity Tokyoを展開しています。
「社会における存在意義」が問われる時代。Identity Tokyoは、志あるブランドのパートナーとして共にパーパスを導き、パーパスを核にブランドを可視化します。今回は、共にパーパスを作り上げたi3DESIGN のデザイン本部執行役員佐々木さん、現在運用に取り組まれているデザイン本部木下さんと、P.K.G.Tokyo代表天野の対談インタビューをお送りします。
取材・文:大島 有貴
撮影:唐 瑞鸿(plana inc.)
策定チームの発足。プロジェクトが動き出す。
天野:本日はよろしくお願いします。i3DESIGN とのお仕事を振り返ると、最初はロゴデザインのご相談をいただいたんですよね。「パーパスから一緒に考えませんか」と私たちからご提案をさせていただきました。
佐々木: そうですね。ちょうど、そのタイミングで弊社代表の芝が会社のフィロソフィーを文章にし始めていたんです。それを原案としてまずは、全社でワークショップを開催しました。当時は社員数20名程度だったので、ちょうどこのフロアで行いましたね。
天野:芝社長、佐々木さんを中心にパーパス策定プロジェクトチームを立ち上げてもらい、そこに弊社の中澤と私が入らせていただきました。ワークショップは2部制で行ったんです。パーパスは企業にだけではなく、個人にもある。その重なりが大きければ大きいほど、その人は企業とマッチしていると考えられています。まずは2人1組になり、会社における個人レベルでのパーパスを可視化してもらいました。その後の第二部では、4、5人のグループで先ほどの個人パーパスを共有しつつ、企業のパーパスについて考えてもらいました。最後に全体で発表し合い、他チームの考えを共有するという内容です。その時に出てきた言葉に傾向はありましたよね。皆さん、「人」や「成長」を意識されていたように思います。そこから、キーワードを抽出していきました。
佐々木:そうですね。そこから芝の言葉や弊社の社風を加味しながら、パーパス策定チームで言葉にまとめていったんです。AからCの3つの案を作りましたね。Aは会社と個人の「成長」が軸に、Bは事業内容が社会にどのような「作用」をもたらすか、Cは弊社の社会における「立場」を明確にしたものでした。そこで決まった初案が「デジタルとクリエイティブの力で世界の進化を支える」という言葉だったのです。
 i3DESIGNのデザイン本部執行役員の佐々木さん(左)、デザイン本部の木下さん(右)。
i3DESIGNのデザイン本部執行役員の佐々木さん(左)、デザイン本部の木下さん(右)。
パーパスから落とし込み、ロゴデザイン制作へ。
天野「i3DESIGN 」の「i」はidentity(アイデンティティ)です。そして、ロゴデザインを制作するにあたり、i3の「3」が何かを定義づけようという話が出てきます。そこにはパーパスの文脈が含まれているべきじゃないかと。そこで、策定チームでディスカッションを行い「ビジネス、デザイン、テクノロジー」の3つのアイデンティティに定義づけをしました。そこから、以前に出ていた言葉と合わせて「Business x Design x Technologyの力で世界の進化を支える」というパーパスができたのです。
天野:既存のロゴは、ちょっと細身でクラシカルな書体で、色は青系を使ってましたよね。ワークショップで出てきた言葉である「人」を意識しました。デジタルUI、UXをやっている会社らしい雰囲気を大切にしながら、人間味を残したんです。色に関しては、パーパスと同時に策定したValueの中にある「Stimulative」“刺激的なパートナーであれ”という言葉から赤を選びました。

人の温かみを感じる「ヒューマニスト・サンセリフ」をオリジナルで設計したロゴタイプ。
社内でパーパスを育ててきたからこそできる、Valueの再策定。
佐々木:実は、現在Valueを新たに社内で作り直しているところなんです。きっかけとして、チームビルディングの一貫で、デザイン本部単位のビジョンとValueを決めたんですよ。デザイナーたちの行動規範というニュアンスですね。それを代表の芝が見ていて、会社のValueも自分たちで見直さないかという話が出たんです。
策定の方法としては、リーダー層や社歴の長い方20人ほどを集めて2回ワークショップを行いました。会社として3年後5年後のなりたい像を明確化し、そのために必要な組織構造は何なのかを考えました。1回目と2回目の間に、私と芝で話し合いも行いましたね。実は、ワークショップの設計と運営は木下に任せているんです。彼女は入社2年目ですが、個人としてよりも組織に対しての意識が高い。加えて、大学時代からワークショップの運営等をしてきた経験があるので指名しました。
木下:最初は緊張しすぎてガチガチでしたね(笑)。オンラインだと、皆さんの熱量が掴みづらいので、かしこまって司会進行をしていたら、皆さんが助けてくださって。全員で取り組んでいる雰囲気に救われましたね。具体的には、会社の未来を描くためには現在を知らないといけないので、現状の良いところと悪いところを書き出してもらいました。そこから未来について皆で考えていったんです。

浸透させることの難しさ、大切さ。
天野:i3DESIGNのすごいところは、一度決めたパーパスを噛み砕き、運用する中で必要であれば社内で調整できることなんですよね。普通は、そのリソースが取れない。弊社のサービスでは「トレーニング」と呼びまして、運用の部分も一緒にお手伝いしています。自主トレできる会社もあれば、トレーナーがいないとトレーニングできない会社もある。それは人員や規模によって変わってくるかと思います。小さな会社ですと社員数が少なく、リソースが取れないですよね。逆に、大企業においては、その大きさゆえに全社員にパーパスを浸透させることが難しいということもあるでしょう。そういったところを、我々はお手伝いすることができるんです。
佐々木:実際の肌感覚として、パーパスが浸透するのって、結構時間がかかるんじゃないかと思います。2年ぐらいは必要かと。私たちも徐々に理解するようになっている感じはあるんです。例えば、採用においては選考基準ができたかなと思っています。入社したけど合わないな、ここが合わせられないと難しいなど、カルチャーマッチの具合がはかれる。そういった定量化できないところが、言語で明確化されていると採用者が拠り所にできるんです。

木下:私が入社時にはもうパーパスが策定されていたのですが、就活の時にウェブサイトを見て印象的だったことは覚えています。私の就活の基準が、UXデザインを取り組んでいる会社かつ、ベンチャーが良かったんです。加えて、パーパスやバリューからのコーポレートサイトの一貫性は見ていました。例えば、デザイン大切だよねって言っている会社なのに、デザインがおかしいところは、ちょっと信用できないのかなと思いましたね。やはり、内側の部分を知るためにはまず、表層的な部分も一致していないと、知る機会さえ持ってもらえないということはあると思います。
天野:若手の方が育っていて、すばらしいですね。御社がパーパスやValueを会社のカルチャーとして定着させるために、取り組んでいることは何かあるのでしょうか。
佐々木:今回、自分たちで作ったValueに関しては、現場で口に出す人が多いような気がします。加えて、部内で毎週M V Pを発表をしているんです。特に賞金とかは出ないんですけど笑。選ぶ基準としては、Valueやミッションに基づいて決めています。今回、一緒に決めてくださったパーパス「Business x Design x Technologyの力で世界の進化を支える」。抽象的な言葉だからこそ、そこに文脈が生まれ、自分たちでValueの策定をした際に役に立ったと感じているんです。これからさらにもう一段、パーパスを浸透させていくためにさまざまなことに取り組んでいきたいと思っています。
天野:お役に立てて嬉しいです。これからも何かのタイミングで協業などできたらいいですね。今日はありがとうございました。

i3DESIGNの情報はこちら
P.K.G.Tokyoが取り組むパーパスブランディング、Identity Tokyoの詳細はこちら